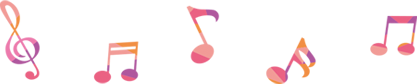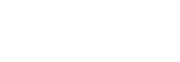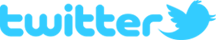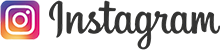合唱のピアノ伴奏オーディション攻略法【part 1.】
小学校や中学校では激戦のピアノ伴奏オーディション!
ピアノ教室でも生徒さんのSOSに対応されていることでしょう。
合唱の伴奏は、ピアノソロと違ったセンスが必要なので、まとめてお話させていただきます。
私は小学校低学年のときに、ピアノが苦手な先生の代わりに授業で伴奏していたことがありました。
今考えるとおかしな話ですが、当時は誇らしく思う反面、音楽の授業で歌えないというもどかしさもありました。
現在は一応公平にオーディションで選ばれます。
ここでは次のようなことについてお話させていただきます。
1.ピアノ伴奏者の心得
2.楽譜が配られてからするべきこと
3.ピアノ伴奏の楽譜に書いていない重要なこと
4.特にミスってはいけない場所
では順にお話させていただきます。
ピアノ伴奏者の心得
ピアノ伴奏者に求められる物は、ずばり安心感です!
・ミスタッチをしない
・テンポが乱れない
・自分の好き勝手に表情を付けない
もちろんピアノが上手なのに越したことはありませんが、悪目立ちするのはいけません。
また、ピアノ伴奏者は縁の下の力持ちではなく、みんなと同じ土俵に立つ演奏者だということをお忘れなく。
例えば混声三部合唱の場合では{(ソプラノ+アルト+男声)とピアノ}ではなく、{ソプラノ+アルト+男声+ピアノ}というように、ピアノを第4のパートとして考えるとよいでしょう。
みんなに合わせるのではなく、みんなと一緒に歌うのです。
楽譜が配られてからするべきこと
楽譜はB5のコピー譜を伴奏の希望者に渡されると思います。
しかし、バラバラの楽譜では練習もしにくいです。
オーディション本番は譜めくりがいらないように、楽譜をつなげておきましょう。
まずはとにかく譜面台にきちんと楽譜が乗るようにすること。
B5だったら、ピアノの譜面台に乗るのは5枚が限界です。
ダラーンと横に長い場合は見栄えも悪いので、つなぐときに空白を切り取って縮めることをおすすめします。
オーディションで、バラバラの楽譜を譜面台に置いていくよりも、1枚につないだ楽譜をサッと置く方がやる気も見せることができるし、時短だし、楽譜が落ちたりする事故が少ないです。
楽譜に台紙を貼っておくと完璧ですが、それはめでたく伴奏者に選ばれてからでもよいでしょう。
とにかくつなげておきましょう。
今回はピアノ伴奏者の心得と、楽譜が配られてからするべきことについてお話させていただきました。
次回はピアノ伴奏の楽譜に書いていない重要なことと、特にミスってはいけない場所についてです。
伴奏オーディションにチャレンジする生徒を指導した時の過去のブログはこちらです。
シーズン到来!小学校のピアノ伴奏者オーディション~1.
シーズン到来!小学校のピアノ伴奏者オーディション~2.
シーズン到来!小学校のピアノ伴奏者オーディション~3.

子どもから大人までピアノ指導する傍ら、本サイト「ピアノサプリ」を開設し運営。【弾きたい!が見つかる】をコンセプトに、演奏効果の高いピアノ曲を1000曲以上、初心者~上級者までレベルごとに紹介。文章を書く趣味が高じて、ピアノファンタジー小説「ピアニーズ」をKindleにて出版。お仕事のお問い合わせはこちらからお願いします。