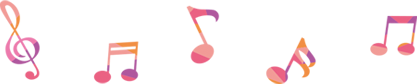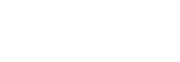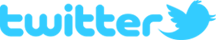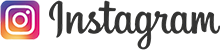演奏でもったいない最後の油断
LINEレッスン(動画によるオンラインレッスン)をしていると、普段の対面レッスンではなかなかわからなかったことに気付くことがあります。
最後の音を弾き終わった後の対応もその一つです。
気をつけないと印象が悪くなるので、特にコンクールや発表会では注意したいですね。
最後にある休符に注意
最後の音が終わっても、その後に休符があるときがあります。
音はなくてもその小節の音楽は続いているということです。
休符を意識した演奏かそうでないかで、それまでの音楽の取り組みがわかるので気をつけましょう。
最後の音符についたフェルマータに注意
フェルマータがあるとき、首や身体を揺らして拍を数える方がいますが、これもダメです。
そもそもフェルマータとはイタリア語で「停止」という意味。
音の流れを止めているのに、身体が揺れているのはおかしいですね。
では、どのくらい停止すればよいのでしょうか?
フェルマータはその音符または休符を、倍に伸ばすと習ったと思います。
しかし、これはきっちりという訳ではありません。
3倍4倍の方がしっくりくる場合もあるし、ほんの気持ちだけということもあります。
これは弾き手の心地の良いところまでということで、感性にゆだねられています。
随分前になりますが、あるピアノの発表会で穏やかな曲を丁寧に弾いていた中学生が、最後の音を聞こえなくなるまで伸ばしていました。
観客は全員息を殺してその音を聴いていました。
曲が弾き終わって、会場から大きな拍手が沸き起こりました。
後で伺うと、発達障害のある生徒さんだということでした。
その生徒さんの感性を大切にしたピアノの先生も素晴らしいですね。
フェルマータの付いた音符の拍を数えるということは、明らかにピアノの先生に6拍とか8拍とか伸ばしなさいと言われるがままに弾いていることが丸わかりです。
例えそのように指導を受けたとしても、練習しているうちに数えなくてもそれくらいにならなければいけません。
最後のペダルに注意
ペダルの踏み方に気をつけていても、離し方が雑だと残念な結果になります。
柔らかく終わりたいのに、残響音がプツンと切れるのはもったいないですね。
曲の雰囲気に応じて、足もゆっくりペダルから離すように心がけましょう。
終止線の上のフェルマータに注意
特にバッハの作品でよく見られるのですが、終止線の上にフェルマータが書かれていることがあります。
これは、音楽の余韻を大事にしましょうということで、曲が終わってからしばらく鍵盤の上で手を待機させてからゆっくり下ろします。
手を膝の上に戻すときも要注意
弾き終わったその手をポンと膝の上に置いていませんか?
元気の良い曲ならまだしも、柔らかく歌う曲でもこういう方が多いです。
結局この曲のことをわかっていないなーということになります。
とりあえず先生に言われたことは全部やり終えたけど、自分の物になるのはもう一息というところでしょうか。
車でドライブをしていて、とても楽しく気持ちよかったのに、目的地に着いたときにガクンと止まるようなものです。
まとめ
せっかく曲を上手に弾いても、最後の最後でがっかりしてしまうこともあります。
最後の休符、フェルマータ、ペダル、終止線の上のフェルマータ、手の戻し方などに注意して、立派に弾き終わりましょう。
「終わりよければすべて良し」という言葉がある通り、終わり方の印象はとても重要です。
終わり方の上手な人は、間違いなく得です!

子どもから大人までピアノ指導する傍ら、本サイト「ピアノサプリ」を開設し運営。【弾きたい!が見つかる】をコンセプトに、演奏効果の高いピアノ曲を1000曲以上、初心者~上級者までレベルごとに紹介。文章を書く趣味が高じて、ピアノファンタジー小説「ピアニーズ」をKindleにて出版。お仕事のお問い合わせはこちらからお願いします。