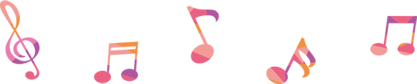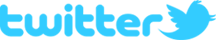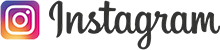簡単音楽史
ピアノの作曲家を中心に、音楽史を古い順に、簡単に説明します。
時代は確実に終わって次に進むのではなく、混ざり合って進行していきます。また、その分類も確実に分かれるのではなく、一人の作曲者の前半生、後半生でも変わってきます。年代についても諸説あるのでご注意ください。
バロック
17世紀(ルネサンス期の終了)~18世紀中頃(バッハの没年頃1750年)です。
イタリアから発展していきました。
それ以前は合唱曲が栄えていましたが、ピアノの前身である鍵盤楽器が発明されたり、名器として名高いストラディヴァリウスのヴァイオリンが生み出されたりに伴って、器楽曲が急速に発達した時代です。
バロック時代の音楽の特徴は、スポンサーである王侯や貴族、教会の意向に沿って作曲しているということです。
したがって豪華絢爛な音楽が好まれました。
バッハの息子達などが、バロック音楽の特徴であったポリフォニー(多声音楽)に代わってホモフォニー(和声音楽)の基礎を作り始めると、J.S.バッハは晩年には時代遅れと評価されるようになります。
J.S.バッハと表記するのは、息子達と区別するためです。
古典派
18世紀中頃(バッハの没年頃1750年)~19世紀初め(ベートーヴェンの没年頃1827年)です。
その頃の音楽の中心地は神聖ローマ帝国の都ウィーンでした。
調性のはっきりした和声音楽が中心となり、ソナタ形式が確立されます。
交響曲(シンフォニー)、協奏曲(コンチェルト)、室内楽曲などもこの時代に多数作曲されています。
前期ロマン派
19世紀初め(ベートーヴェンの没年頃1827年)~19世紀中頃です。
ピアノの発達により、ピアノ作品が数多く作られます。
今までは宮廷や教会で活動することが多かった音楽家たちが、形式にとらわれない自由な音楽を作り発表するようになりました。
曲に感情が盛り込まれ、標題が付いた音楽が次々と誕生し、主にパリで栄えました。
ベートーヴェン、シューベルトも前期ロマン派に含まれるという説もあります。
後期ロマン派
19世紀後半です。
後期ロマン派にはチャイコフスキーや、前期ロマン派から活躍している長命なリストもいます。
また、自国の民族音楽を取り入れる新しい音楽「国民楽派」も誕生しました。
ロシアのムソルグスキー、北欧のシベリウスやグリーグ、スペインのアルベニスなどです。
前期ロマン派の自由な作風が進み、さらに前衛的な音楽が生まれる一方で、古典派を尊重しながらロマン的な表現を追及する「新古典派」もドイツで生まれました。
ブラームスもその代表格です。
印象派
19~20世紀初めです。
ロマン派から発展した、光、水、風などのイメージを音に取り入れた新しい音楽です。
フランス中心に栄えました。
近代
19世紀後半から第二次世界大戦終了です。
ロマン派を可能性を追求した新ロマン主義のラフマニノフ、ロマン主義を否定したシェーンベルク、原始主義のストラヴィンスキーなど、様々な個性を持った音楽が誕生し発展します。
スクリャービン、カバレフスキー、シマノフスキも近代を代表する作曲家です。
現代
第二次世界大戦後です。
クラシック音楽からはみ出す試みが、様々なジャンルの音楽を生み出します。
電子音楽も誕生し、ますます可能性が広がりました。
複雑なリズムや不協和音を用い、調性も崩壊し、メロディらしきものも見つけられないような難解な音楽になって行きます。

子どもから大人までピアノ指導する傍ら、本サイト「ピアノサプリ」を開設し運営。【弾きたい!が見つかる】をコンセプトに、演奏効果の高いピアノ曲を1000曲以上、初心者~上級者までレベルごとに紹介。文章を書く趣味が高じて、ピアノファンタジー小説「ピアニーズ」をKindleにて出版。お仕事のお問い合わせはこちらからお願いします。