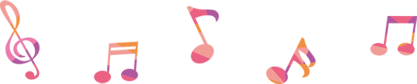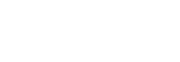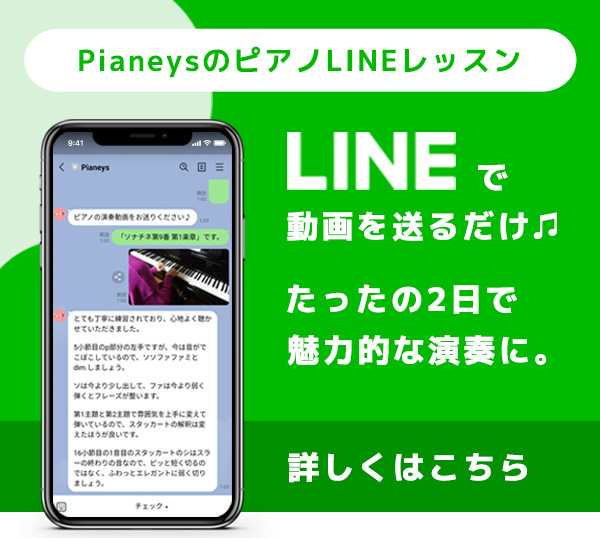耳コピは聴音でトレーニング!やり方とコツを解説
テレビやYouTubeなどで流れた音楽を自分で演奏したいと思ったことはありませんか?
その都度楽譜を買うのも良いですが、もし耳コピができれば、手軽に好きな音楽を自分で楽しむことができます。
このページでは、耳コピのやり方・コツと、耳コピするために必要な聴音のトレーニング方法を解説します。
耳コピって何?
音楽を耳で聴いてコピーすることを俗語で耳コピと言います。
多くの人の耳コピする理由は、好きな音楽を気軽に演奏したいからだと思います。
演奏されている音を聴いて覚えて自分で演奏すること、その音を譜面に起こすこと、DAWに打ち込むこと、すべてが耳コピです。
楽器で確認しながら行うので、絶対音感がなくてもできます。
耳コピで音感は鍛えられる?
もちろん耳コピは音感のトレーニングにもなります。
例えば、好きな歌は楽譜がなくても覚えて歌うことができますね?
そのメロディーをピアノなどで弾いてみることが耳コピです。
まず、最初の音を取るところから始めてみましょう。
いきなり複雑な曲はハードルが高いので、童謡など少ない音の短い曲で訓練していきましょう。
耳コピでは楽譜に音を書いても書かなくてもどちらでもかまいません。
しかし、いつまでも音を記憶しておく自信のない方は、楽譜に書いて残しておくことをオススメします。
これを聴音と言います。
耳コピのやり方は楽器編成で異なる
耳コピはメロディーだけ取るものから、色々な楽器編成(バンドなど)の音すべてを取るものまであります。
複数の楽器編成の曲を耳コピする場合は、一つの楽器の音を集中して聴いて取るのが一般的です。
まずはボーカルとギターやボーカルとピアノのように弾き語り的な曲から始めてみましょう。
はじめにボーカルの部分だけ、自分の持っている楽器の助けを借りながら耳コピします。
最初の音が取れれば手探り状態で次に進めると思います。
音は忘れないようにメモしておきましょう。
次に音源を確かめながらメロディーに合うコードを探していきます。
基本的なコード進行のパターンを知識として押さえておく必要があり、その方が近道です。
4人編成のバンド(例:ボーカル・ギター・ベース・ドラムス)の曲を耳コピするときは、まずボーカルのメロディーだけを集中して聴いて取ります。
次にベース音だけを取ります。
ベースがコードのルートになっているので、そこからコードが推測できます。
最後に打楽器などのリズムを入れていきます。
メロディーとコードネームだけを聴き取ってメモし、後は似た感じにアドリブでおこなうのも耳コピです。
また、1つのメロディーに対してコードは無限に展開できるので、メロディーだけ耳コピして、あなたのセンスでコードを考えてみるのもよいでしょう。
耳コピから聴音へ
耳コピを鍛えるには音感トレーニングがかかせません。
また、音を忘れないようにするために、やはり楽譜が書けるに越したことはありません。
それには、音を聴いて楽譜に書き取る聴音が最適です。
聴音のトレーニングは大きく分けて旋律聴音と和声聴音の2種類があります。
旋律聴音とは、メロディーを聴き取ることで、和声聴音は和音を聴き取ることです。
耳コピの場合、ボーカルの旋律を聴き取ることが旋律聴音、ギターなどのコードを聴き取ることが和声聴音になります。
また、拍子、調、音符などについて理解した上で耳コピする方がスムーズに音が頭に入るので、楽典(音楽理論)の知識も必要になってきます。
もちろん何度も何度も繰り返し聴かなければなりませんが、今はYouTubeなども利用できるので便利です。
聴音にはルールがある
音楽系学校の入試や大手楽器店の音楽講師の試験には聴音は必須です。
課題には一定の様式があります。
・出題の直前に音部記号(ト音記号またはヘ音記号)、小節数(4小節単位で増減)、何分の何拍子か?何調か?を提示される
・ほとんどの場合、基準音または基準となる和音(ハ長調なら「ド」または「ドミソの和音」)を提示される
・はじめにメトロノーム音があり、1拍の長さをわかりやすくしている場合もある
・決まった回数で取る
聴音とは五線譜に音符を書き込んで楽譜を作成することなので、楽譜に対する知識が必要です。
また、和声聴音ではコード進行の知識もあった方が便利です。
独学での音感トレーニングでは、できるまで何度でも聴いてみるのも大切ですが、答え合わせをした後に、できなかったところを理解できるまで何度も聴き直すことがさらに重要です。
旋律聴音と和声聴音で音感を鍛える
音感を鍛えるための旋律聴音と和声聴音の問題を作りましたので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください♪
まとめ
耳コピとは音楽を耳で聴いてコピーすることです。
そして、耳コピを鍛えるには音感トレーニングがかかせません。
いきなり複雑な曲はハードルが高いので、まずは童謡など少ない音の短い曲で訓練していきましょう。
複数の楽器編成の曲(バンドなど)を耳コピする場合は、一つの楽器の音を集中して聴いて取るのが一般的です。
メロディーとコードネームだけを聴き取ってメモし、後は似た感じにアドリブでおこなうのも耳コピです。
音を忘れないようにするためには、やはり楽譜が書けるに越したことはありません。
それには、音を聴いて楽譜に書き取る聴音が最適です。
旋律聴音や和声聴音で音感を鍛えて、耳コピ能力を高めましょう!
【あなたにオススメの関連記事】

子どもから大人までピアノ指導する傍ら、本サイト「ピアノサプリ」を開設し運営。【弾きたい!が見つかる】をコンセプトに、演奏効果の高いピアノ曲を1000曲以上、初心者~上級者までレベルごとに紹介。文章を書く趣味が高じて、ピアノファンタジー小説「ピアニーズ」をKindleにて出版。お仕事のお問い合わせはこちらからお願いします。